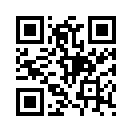2012年09月28日
二十四節季と新しい季節のことば
秋分を過ぎ、ようやく過ごしやすい気候になってきました。
暑い夏を彩ってくれた槿(むくげ)や百日紅(さるすべり)の花も少なくなり、
秋桜(コスモス)が野原で優しく揺れています。虫の音も賑やかなこの頃です。

「秋分」は、御存じの通り、二十四節季(にじゅうしせっき)における季節を表す言葉です。
二十四節季は、節分を基準に1年を24等分して約15日ごとに分けた季節のことですが、
元は中国で使われていた、月の満ち欠けに基づいた太陰暦が、太陽の位置と無関係なため、
春夏秋冬といった季節との間にズレが生じてしまい、そこで本来の季節を知る目安として、
中国の戦国時代に導入されたものでした。
日本では、江戸時代から暦に取り入れられ、秋分の他にも、冬至や夏至、春分など、
私たちの日常でお馴染みなものもあれば、啓蟄、清明、白露など、手紙や俳句の季語で
見かける程度で、馴染みの薄いものもあります。
二十四節季自体が中国の気候をもとにつくられたものですから、日本の季節や時期とあわない言葉もあります。
そこで、昨冬より、日本気象協会でより親しみを感じられる「日本版二十四節気~新しい季節のことば~」づくりが
始まりました。選任された識者のリードのもと、多くの意見や提案を取り入れながら、進めていくこのプロジェクト、
大変、興味深い試みではないかと思います。
一方で、二十四節季自体が長く日本で暦や俳句で馴染み、農家の方々の農作の目安にもなってきたもので、
日本文化の一部になってきたものでもありますから、日本気象協会では、新しく二十四節季をつくるというより、
二十四節季をわかりやすく伝え直すこと、そして四季豊かな日本の気候や生活、文化にあった
「新しい季節のことば」づくりに重点を置きながら、プロジェクトを進めていかれる様子です。
ご興味があれば、プロジェクトの様子を見守られたり、また、名案があれば、ご投稿されてはいかがでしょうか。
どんな言葉が「新しい季節のことば」に選ばれるか、とても楽しみです。
【外部サイトリンク】
「暦の上では」(日本気象協会サイト): http://24setuki.com
「二十四節季」(日本文化いろは辞典): http://iroha-japan.net/iroha/A04_24sekki

暑い夏を彩ってくれた槿(むくげ)や百日紅(さるすべり)の花も少なくなり、
秋桜(コスモス)が野原で優しく揺れています。虫の音も賑やかなこの頃です。
「秋分」は、御存じの通り、二十四節季(にじゅうしせっき)における季節を表す言葉です。
二十四節季は、節分を基準に1年を24等分して約15日ごとに分けた季節のことですが、
元は中国で使われていた、月の満ち欠けに基づいた太陰暦が、太陽の位置と無関係なため、
春夏秋冬といった季節との間にズレが生じてしまい、そこで本来の季節を知る目安として、
中国の戦国時代に導入されたものでした。
日本では、江戸時代から暦に取り入れられ、秋分の他にも、冬至や夏至、春分など、
私たちの日常でお馴染みなものもあれば、啓蟄、清明、白露など、手紙や俳句の季語で
見かける程度で、馴染みの薄いものもあります。
二十四節季自体が中国の気候をもとにつくられたものですから、日本の季節や時期とあわない言葉もあります。
そこで、昨冬より、日本気象協会でより親しみを感じられる「日本版二十四節気~新しい季節のことば~」づくりが
始まりました。選任された識者のリードのもと、多くの意見や提案を取り入れながら、進めていくこのプロジェクト、
大変、興味深い試みではないかと思います。
一方で、二十四節季自体が長く日本で暦や俳句で馴染み、農家の方々の農作の目安にもなってきたもので、
日本文化の一部になってきたものでもありますから、日本気象協会では、新しく二十四節季をつくるというより、
二十四節季をわかりやすく伝え直すこと、そして四季豊かな日本の気候や生活、文化にあった
「新しい季節のことば」づくりに重点を置きながら、プロジェクトを進めていかれる様子です。
ご興味があれば、プロジェクトの様子を見守られたり、また、名案があれば、ご投稿されてはいかがでしょうか。
どんな言葉が「新しい季節のことば」に選ばれるか、とても楽しみです。
【外部サイトリンク】
「暦の上では」(日本気象協会サイト): http://24setuki.com
「二十四節季」(日本文化いろは辞典): http://iroha-japan.net/iroha/A04_24sekki
Posted by 菊池建設 藤沢 at 10:10│Comments(0)