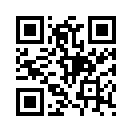2012年11月10日
最小限住居考(その3) 避難所と仮設住宅
昨年3月11日に発生した東日本大震災。今も鮮明に災害の爪痕、衝撃が
脳裏に焼き付いています。そして、多くの被災者の方々が、今も仮設住宅に
住まわれています。未だ被災地の復興、並びに被災者の生活再建の途上です。
スピーディかつ着実な被災地の震災復興、並びに被災者の生活再建を心より願いながら、
今回は、大災害の後に被災者の生命と生活を支える役割を担う、
避難所と仮設住宅についてお話しします。

地震や津波、水害、山崩れといった自然災害の被害を受けた生存者のうち、
治療等で入院の必要のない被災者の多くは、まず近隣の公共の体育館などの
避難所に避難し、一定期間を過ごします。

しかしながら、ご存じの通り、避難所はあくまで一時避難の場所です。
水や食料がそれなりに用意され、雨風を防いだ居場所や寝場所、トイレなどは
ありますが、衛生面やプライバシー等の問題があり、長期間の生活には向きません。
実際に避難所において、感染性の病気にかかったり、精神的なストレスでダメージを
受けた方は決して少なくありません。
避難所は、人間として「生命」を維持できる最低限の場ではありますが、
「生活」を維持できる場所ではないのでしょう。避難所は「住居」とはなりえないのです。
そこで、移転先のない被災者の多くは、避難所から仮設住宅に移り住みます。

「仮設住宅」という名は通称で、日本での正式名称は「応急仮設住宅」と言います。
自然災害等で居住する家屋を失い、すぐに住宅を得ることのできない被災者に対し、
国や地方自治体等が、原則2年という期間で貸与する仮設の住宅のことです。
避難所に比べると、それなりの生活ができますので、仮設住宅は一応「住居」と言えます。
しかし、仮設住宅は、被災者のために災害後迅速な建築が求められると共に、原則2年後には
撤去する予定のため、多くの仮設住宅は、被災者の長期生活を予定していません。
また、国や自治体にも予算の限度があるために、多くの仮設住宅は、プレハブを中心とした、
簡素な仮の住居であることは否めません。
そのため、実際に仮設住宅に住む上では、住みにくさや使いにくさがあり、具体的には、
断熱性や段差、雨漏り、水捌け、虫の発生等の物理的な問題があったり、
コミュニティの分断や精神的なストレスからの孤独死等の社会的、精神的な問題もあります。
被災者は、自然災害から生命の危機を逃れ、ようやく仮設住居での生活が始まったとしても、
大切な家族や知人、コミュニティを失い、住まいや財産、大切なものを失い、
仕事や収入を失い、暮らしの中で慣れ親しみ、長い年月を経て築き、蓄えてきた様々なものを
失うという、物理的・精神的に大変大きなダメージを受けています。
では、被災者がダメージから回復し、新たな生活の支えとなるような仮設住宅の
企画・建設は可能でしょうか。
阪神淡路大震災以後、日本だけでなく、世界各地での仮設住宅の建築の設計、建築に
関わってきた坂 茂(ばん しげる)という建築家がいます。坂氏の取組みが新しい仮設住宅の
大きなヒントになりえると思いますので、ここで紹介いたします。
まず、阪神淡路大震災時の坂氏設計の「紙のログハウス」という仮設住宅をご覧ください。

2001年のインド西部大地震の際の紙のログハウスです。

ちなみに、坂氏が試行錯誤の末に生み出した避難所のパーティションがこれです。

夏はネットをかけて蚊帳ともなります。避難所のプライバシーや居住性を
簡素かつ美しい造形で改善しています。
そして、東日本大震災後に宮城県女川町で実現したコンテナを構造躯体に利用した、
3階建の仮設住宅です。


完成した外観は低層の公営団地に近いものがあります。そして、室内は住みやすい機能性、
また、無印住宅と言えるようなシンプルな美しさを合わせもっています。
このコンテナ多層型仮設住宅は、全部で189戸、敷地内にはマーケットや教室(アトリエ)も
寄贈され、コミュニティの形成にも配慮されています。
他にも多くの地震や津波の復興支援の仮設住宅、仮設教室、避難シェルター、復興住宅等に
坂氏は関わってこられました。住環境、コミュニティ、コスト、自力建設、地域経済等、
様々な課題を意識しながら、復興支援のために尽力されてきた姿勢は素晴らしいと思います。
ただ、これは坂茂氏という一建築家の取組みであり、施工案件は限られています。
住環境、コミュニティ、施工・解体性、コスト面等様々な面で、建築家や施工会社、メーカー、
そして、国や地方自治体等が協力し、よりベストなものを求めながら、非常時に備える必要があります。
鴨長明は平安末期の天災や戦災で受けた大きな衝撃や自らの人生を振り返り、
個人レベルでの仮設住居であり、終の住処としての方丈庵を完成させ、生涯住み続けました。
避難所や仮設住宅は、非常時において、個人レベルでの生命、生活の器としての
住居や住環境について考え、備えなくてはならない課題と共に、国や地方自治体、
コミュニティといった集団レベルでの居住や住環境について考え、備えるべき課題を提起しています。
明日は我が身。非常時の住居を考え、備える必要が誰にでもあるのです。

<最小限住居考 バックナンバー>
その1 方丈庵 http://kikuchif.hama1.jp/e991016.html
その2 「ウォールデン」森の小屋 http://kikuchif.hama1.jp/e991424.html
<外部リンク>
国土交通省 応急仮設住宅関連情報 http://www.mlit.go.jp/report/daisinsai_kasetu.html
プレハブ応急仮設住宅の現状と抱える問題 SAREX (PDF) http://www.sarex.or.jp/kasetuteian.pdf
坂茂建築設計 災害支援プロジェクト http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_DRP/SBA_DRP_index.htm
脳裏に焼き付いています。そして、多くの被災者の方々が、今も仮設住宅に
住まわれています。未だ被災地の復興、並びに被災者の生活再建の途上です。
スピーディかつ着実な被災地の震災復興、並びに被災者の生活再建を心より願いながら、
今回は、大災害の後に被災者の生命と生活を支える役割を担う、
避難所と仮設住宅についてお話しします。

地震や津波、水害、山崩れといった自然災害の被害を受けた生存者のうち、
治療等で入院の必要のない被災者の多くは、まず近隣の公共の体育館などの
避難所に避難し、一定期間を過ごします。

しかしながら、ご存じの通り、避難所はあくまで一時避難の場所です。
水や食料がそれなりに用意され、雨風を防いだ居場所や寝場所、トイレなどは
ありますが、衛生面やプライバシー等の問題があり、長期間の生活には向きません。
実際に避難所において、感染性の病気にかかったり、精神的なストレスでダメージを
受けた方は決して少なくありません。
避難所は、人間として「生命」を維持できる最低限の場ではありますが、
「生活」を維持できる場所ではないのでしょう。避難所は「住居」とはなりえないのです。
そこで、移転先のない被災者の多くは、避難所から仮設住宅に移り住みます。

「仮設住宅」という名は通称で、日本での正式名称は「応急仮設住宅」と言います。
自然災害等で居住する家屋を失い、すぐに住宅を得ることのできない被災者に対し、
国や地方自治体等が、原則2年という期間で貸与する仮設の住宅のことです。
避難所に比べると、それなりの生活ができますので、仮設住宅は一応「住居」と言えます。
しかし、仮設住宅は、被災者のために災害後迅速な建築が求められると共に、原則2年後には
撤去する予定のため、多くの仮設住宅は、被災者の長期生活を予定していません。
また、国や自治体にも予算の限度があるために、多くの仮設住宅は、プレハブを中心とした、
簡素な仮の住居であることは否めません。
そのため、実際に仮設住宅に住む上では、住みにくさや使いにくさがあり、具体的には、
断熱性や段差、雨漏り、水捌け、虫の発生等の物理的な問題があったり、
コミュニティの分断や精神的なストレスからの孤独死等の社会的、精神的な問題もあります。
被災者は、自然災害から生命の危機を逃れ、ようやく仮設住居での生活が始まったとしても、
大切な家族や知人、コミュニティを失い、住まいや財産、大切なものを失い、
仕事や収入を失い、暮らしの中で慣れ親しみ、長い年月を経て築き、蓄えてきた様々なものを
失うという、物理的・精神的に大変大きなダメージを受けています。
では、被災者がダメージから回復し、新たな生活の支えとなるような仮設住宅の
企画・建設は可能でしょうか。
阪神淡路大震災以後、日本だけでなく、世界各地での仮設住宅の建築の設計、建築に
関わってきた坂 茂(ばん しげる)という建築家がいます。坂氏の取組みが新しい仮設住宅の
大きなヒントになりえると思いますので、ここで紹介いたします。
まず、阪神淡路大震災時の坂氏設計の「紙のログハウス」という仮設住宅をご覧ください。

2001年のインド西部大地震の際の紙のログハウスです。

ちなみに、坂氏が試行錯誤の末に生み出した避難所のパーティションがこれです。

夏はネットをかけて蚊帳ともなります。避難所のプライバシーや居住性を
簡素かつ美しい造形で改善しています。
そして、東日本大震災後に宮城県女川町で実現したコンテナを構造躯体に利用した、
3階建の仮設住宅です。


完成した外観は低層の公営団地に近いものがあります。そして、室内は住みやすい機能性、
また、無印住宅と言えるようなシンプルな美しさを合わせもっています。
このコンテナ多層型仮設住宅は、全部で189戸、敷地内にはマーケットや教室(アトリエ)も
寄贈され、コミュニティの形成にも配慮されています。
他にも多くの地震や津波の復興支援の仮設住宅、仮設教室、避難シェルター、復興住宅等に
坂氏は関わってこられました。住環境、コミュニティ、コスト、自力建設、地域経済等、
様々な課題を意識しながら、復興支援のために尽力されてきた姿勢は素晴らしいと思います。
ただ、これは坂茂氏という一建築家の取組みであり、施工案件は限られています。
住環境、コミュニティ、施工・解体性、コスト面等様々な面で、建築家や施工会社、メーカー、
そして、国や地方自治体等が協力し、よりベストなものを求めながら、非常時に備える必要があります。
鴨長明は平安末期の天災や戦災で受けた大きな衝撃や自らの人生を振り返り、
個人レベルでの仮設住居であり、終の住処としての方丈庵を完成させ、生涯住み続けました。
避難所や仮設住宅は、非常時において、個人レベルでの生命、生活の器としての
住居や住環境について考え、備えなくてはならない課題と共に、国や地方自治体、
コミュニティといった集団レベルでの居住や住環境について考え、備えるべき課題を提起しています。
明日は我が身。非常時の住居を考え、備える必要が誰にでもあるのです。

<最小限住居考 バックナンバー>
その1 方丈庵 http://kikuchif.hama1.jp/e991016.html
その2 「ウォールデン」森の小屋 http://kikuchif.hama1.jp/e991424.html
<外部リンク>
国土交通省 応急仮設住宅関連情報 http://www.mlit.go.jp/report/daisinsai_kasetu.html
プレハブ応急仮設住宅の現状と抱える問題 SAREX (PDF) http://www.sarex.or.jp/kasetuteian.pdf
坂茂建築設計 災害支援プロジェクト http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_WORKS/SBA_DRP/SBA_DRP_index.htm
Posted by 菊池建設 藤沢 at 09:48│Comments(0)