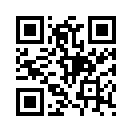2012年06月11日
古い土蔵
藤沢市内を走っていると、土蔵を時々見かけます。
修理してあるものや写真のように痛んだままのもの。
現在では貴重な建物で有るのですが、修理されずにそのままになっています。
いろいろな事情があるのでしょう。
下記は参考にご覧下さい。
土蔵(どぞう)とは、日本の伝統的な建築様式のひとつで、外壁を土壁として漆喰などで仕上げられるもの。日常では単に蔵(くら)とよばれることが多く、この様式で作られた建物は土蔵造り・蔵造りなどといわれる。倉庫や保管庫として建てられるもののほか、保管庫と店舗を兼ねて建てられるものもある。店舗・住居を兼ねるものは「見世蔵(店蔵)」と呼ばれることもあり、倉庫・保管庫として建てられるものとは分化して発展してきた。
起源ははっきりとはしない。中世にも町屋などと共に建てられており、近世、鉄砲の伝来の影響により城郭にも防火・防弾のために漆喰大壁の技術が用いられ、30cm以上の分厚い壁を多用したことで安土桃山時代後期から江戸期前後の櫓や天守などの防御施設は土蔵造りとなった。江戸時代以降には、城郭で発展した技術も生かされ、火災や盗難防止のために盛んに建てられ、後に裕福さの象徴ともなった。明治以降には、土壁の上に漆喰ではなくモルタルを塗り洋風に仕上げられることもあった。また、土壁ではなく煉瓦や大谷石で造られたものもある。現在は、伝統的な外観を生かして、飲食店などの商業施設や博物館に転用されることもある。
見世蔵(みせぐら)は、江戸時代以降に発展した商家建築の様式の一種で、土蔵の技術を応用したもの。土蔵の一種ではあるものの、用途が異なることから、枝分かれするかたちで独自の発展を遂げた。
商品などの保管・貯蔵を目的とした土蔵とは異なり、見世蔵は、店舗兼住宅として使うことを目的として建てられるもので、土蔵とは開口部の作り方や間取り・内装が異なる。
土蔵の場合は、開口部をなるべく小さくし、耐火壁の部分を多く取って、耐火性能を向上させることを重視して設計される。また内部も、保管・収蔵を目的としているため、細かい間取りなどはなされない。対して見世蔵の場合は、店舗・住居として使うことを主目的としているため、耐火性能面では多少の妥協がなされ、商店部分の間口や住居部分の窓などの開口部が設けられている。内部の間取りなども通常の商店建築に準ずる。
土蔵のほか石蔵の様式を採用したもの、明治時代以降には煉瓦蔵の様式を採用したものや漆喰のかわりにモルタルやコンクリートを使ったものなども見られる。
古い宿場町・商都などにはある程度残されているが、近年では観光資源としての積極的な利用に転じている事例もある。
川越市に現存する見世蔵 ↓
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Store_of_the_godown_style%2CKawagoe-city%2CJapan.jpg/220px-Store_of_the_godown_style%2CKawagoe-city%2CJapan.jpg
Posted by 菊池建設 藤沢 at
17:58
│Comments(0)
2012年06月11日
森林浴
キャンプ会場の下見に、森の中へ行ってきました。


森林香りと川の流れの音に癒されました・・・。
梅雨入りしましたが、キャンプ当日は晴れるといいな


森林香りと川の流れの音に癒されました・・・。
梅雨入りしましたが、キャンプ当日は晴れるといいな

Posted by 菊池建設 藤沢 at
10:34
│Comments(0)