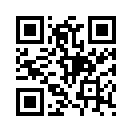2013年02月01日
最小限住居考(その6) 洞窟住居と竪穴式住居
本年最初の「最小限住居考」。今回は「洞窟住居と竪穴式住居」についてお話しします。

人気のテレビ企画「無人島生活」をご覧になったことはありませんか?
よゐこや他の芸能人達が無人島でサバイバル生活を送る様子がとても面白いですね。
無人島生活を見ていて興味ひかれるものの一つが、毎回作られる小屋が様々であるということ。
長期滞在するわけではないので、雨風や寒さをしのぐ程度の簡素なものが多いのですが、
道具や材料が限られている中で、色々と工夫をして小屋を作られています。
一方で、これは創作の物語ですが、児童文学の古典、ジュール・ヴェルヌ「十五少年漂流記」は、
無人島に漂着した少年たちが島で暮らす、2年間の波乱に満ちた日々について描かれたものです。

少年たちがチェアマン島と名付けた島で住居に選んだのは、洞穴(洞窟)でした。
洞窟は、材料を用意して一から小屋を建てることなく住むことができますので、
建築の手間を省きながら、構造的な心配も少ないという利点がありました。
実際に、人類が遥か昔から住居として洞窟を利用してきたという歴史があります。
イタリアのマテーラ、トルコのカッパドキアの洞窟住居は、世界遺産として有名で、
今も住居や商業施設として利用されています。


ただ、洞窟住居は、立地が岩山であることが多く、また、掘りやすいこと、構造的に安定して
いる(崩れにくい)ことといった条件がつきます。
また、今でこそ換気設備が当たり前のように住居に付帯していますが、
古代の洞窟住居の中での火の扱いは慎重で、調理は主に洞窟の外で行われていたようです。
入口さえ塞いでしまえば、猛獣などの侵入も防げますし、冬暖かく、夏涼しいという利点もありました。
一方で、岩山や洞窟の少ない地域において、古代の人類が築いた住まいが「竪穴式住居」でした。
歴史の授業などで習った竪穴式住居というとこんな形を思い浮かべませんか?

しかし、こんな立派な形の竪穴式住居は、時代的に遅い段階のもののようです。
古代の人々が雨風や寒暖をしのぐために作った住居は、
岩や木に、木を立て掛けたり、窪地に木を渡したりして、枝をくくり、その上に
草や葉や土を乗せたような簡素なものだったと考えられます。(岩陰住居)
それが時代を経て、より作りやすく、安心して利用できるように発展したものが
初期の竪穴式住居だったようです。地域差はありますが、数十cmほどの窪地に、
扠首(さす、斜めに支えあう)状に木を建て、枝を渡し、草や葉や土を乗せたものだったようです。

簡素な竪穴式住居だと、天井高が低く、広さも限られます。安全性を考えれば、
住居内での火の取扱いも慎重になります。とはいえ、獲物の狩猟や、
木の実の採取等で生活している場合は、食物の在り処や季節によって
移住しなければならない場合もあったでしょう。その場合、作りやすい住居ということが
大きな条件となってきます。
しかしながら、後に、稲や作物の栽培が活発になると、人々は栽培地の近くに
定住するようになり、集落といった共同体を作るようになります。
定住するので、移住を考えた作りやすさの簡便性よりも、定住するための居住性や
より壊れにくい安全性を求めるようになります。
地面をより深く掘り、掘った回りに土を盛り、柱を建て、棟木や梁を渡し、時には小屋組を設け、
垂木や扠首を掛け、内部の空間を広く、天井高を高くします。
そして、調理や暖を取るための炉を設け、排煙(排気)口も設けます。
建築の手間はかかりますが、集落の人手は多く、協力しながら、住居を作ることができます。


古代の人類の住居は、自然環境において身を守るシェルターの役割を果たしていた
洞窟住居や簡素な小屋から始まり、長い時を経て、竪穴式住居まで進化しました。
日本においては、竪穴式住居が多く普及し、後代に南方から伝わった高床式住居も交え、
木造の掘建柱(ほったてばしら)建物へと発展していきます。一方で西洋などでは、
石や煉瓦の組積造を主体に、一部木造も交えながら、発展していきます。
現代の日本の木造軸組工法の住まいは、古代の知恵と息吹、歴史や文化の流れを踏まえ、
この国の気候風土等を考慮し、成立した建物だと考えますと、とても感慨深いものがあります。
興味がありましたら、お近くの竪穴式住居をご覧になられてはいかがでしょうか。

<最小限住居考 バックナンバー>
その1 方丈庵 http://kikuchif.hama1.jp/e991016.html
その2 「ウォールデン」森の小屋 http://kikuchif.hama1.jp/e991424.html
その3 避難所と仮設住宅 http://kikuchif.hama1.jp/e991793.html
その4 「あしたのジョー」のドヤ街 http://kikuchif.hama1.jp/e993015.html
その5 トキワ荘の青春と江戸人情長屋 http://kikuchif.hama1.jp/e995236.html

人気のテレビ企画「無人島生活」をご覧になったことはありませんか?
よゐこや他の芸能人達が無人島でサバイバル生活を送る様子がとても面白いですね。
無人島生活を見ていて興味ひかれるものの一つが、毎回作られる小屋が様々であるということ。
長期滞在するわけではないので、雨風や寒さをしのぐ程度の簡素なものが多いのですが、
道具や材料が限られている中で、色々と工夫をして小屋を作られています。
一方で、これは創作の物語ですが、児童文学の古典、ジュール・ヴェルヌ「十五少年漂流記」は、
無人島に漂着した少年たちが島で暮らす、2年間の波乱に満ちた日々について描かれたものです。

少年たちがチェアマン島と名付けた島で住居に選んだのは、洞穴(洞窟)でした。
洞窟は、材料を用意して一から小屋を建てることなく住むことができますので、
建築の手間を省きながら、構造的な心配も少ないという利点がありました。
実際に、人類が遥か昔から住居として洞窟を利用してきたという歴史があります。
イタリアのマテーラ、トルコのカッパドキアの洞窟住居は、世界遺産として有名で、
今も住居や商業施設として利用されています。


ただ、洞窟住居は、立地が岩山であることが多く、また、掘りやすいこと、構造的に安定して
いる(崩れにくい)ことといった条件がつきます。
また、今でこそ換気設備が当たり前のように住居に付帯していますが、
古代の洞窟住居の中での火の扱いは慎重で、調理は主に洞窟の外で行われていたようです。
入口さえ塞いでしまえば、猛獣などの侵入も防げますし、冬暖かく、夏涼しいという利点もありました。
一方で、岩山や洞窟の少ない地域において、古代の人類が築いた住まいが「竪穴式住居」でした。
歴史の授業などで習った竪穴式住居というとこんな形を思い浮かべませんか?

しかし、こんな立派な形の竪穴式住居は、時代的に遅い段階のもののようです。
古代の人々が雨風や寒暖をしのぐために作った住居は、
岩や木に、木を立て掛けたり、窪地に木を渡したりして、枝をくくり、その上に
草や葉や土を乗せたような簡素なものだったと考えられます。(岩陰住居)
それが時代を経て、より作りやすく、安心して利用できるように発展したものが
初期の竪穴式住居だったようです。地域差はありますが、数十cmほどの窪地に、
扠首(さす、斜めに支えあう)状に木を建て、枝を渡し、草や葉や土を乗せたものだったようです。

簡素な竪穴式住居だと、天井高が低く、広さも限られます。安全性を考えれば、
住居内での火の取扱いも慎重になります。とはいえ、獲物の狩猟や、
木の実の採取等で生活している場合は、食物の在り処や季節によって
移住しなければならない場合もあったでしょう。その場合、作りやすい住居ということが
大きな条件となってきます。
しかしながら、後に、稲や作物の栽培が活発になると、人々は栽培地の近くに
定住するようになり、集落といった共同体を作るようになります。
定住するので、移住を考えた作りやすさの簡便性よりも、定住するための居住性や
より壊れにくい安全性を求めるようになります。
地面をより深く掘り、掘った回りに土を盛り、柱を建て、棟木や梁を渡し、時には小屋組を設け、
垂木や扠首を掛け、内部の空間を広く、天井高を高くします。
そして、調理や暖を取るための炉を設け、排煙(排気)口も設けます。
建築の手間はかかりますが、集落の人手は多く、協力しながら、住居を作ることができます。


古代の人類の住居は、自然環境において身を守るシェルターの役割を果たしていた
洞窟住居や簡素な小屋から始まり、長い時を経て、竪穴式住居まで進化しました。
日本においては、竪穴式住居が多く普及し、後代に南方から伝わった高床式住居も交え、
木造の掘建柱(ほったてばしら)建物へと発展していきます。一方で西洋などでは、
石や煉瓦の組積造を主体に、一部木造も交えながら、発展していきます。
現代の日本の木造軸組工法の住まいは、古代の知恵と息吹、歴史や文化の流れを踏まえ、
この国の気候風土等を考慮し、成立した建物だと考えますと、とても感慨深いものがあります。
興味がありましたら、お近くの竪穴式住居をご覧になられてはいかがでしょうか。

<最小限住居考 バックナンバー>
その1 方丈庵 http://kikuchif.hama1.jp/e991016.html
その2 「ウォールデン」森の小屋 http://kikuchif.hama1.jp/e991424.html
その3 避難所と仮設住宅 http://kikuchif.hama1.jp/e991793.html
その4 「あしたのジョー」のドヤ街 http://kikuchif.hama1.jp/e993015.html
その5 トキワ荘の青春と江戸人情長屋 http://kikuchif.hama1.jp/e995236.html
Posted by 菊池建設 藤沢 at 09:27│Comments(0)